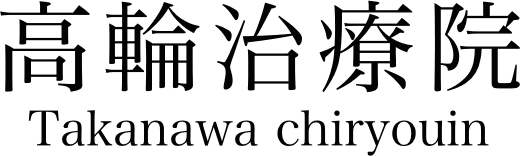足のつり

先日、来院した70代の写真家の患者さんが「久しぶりに一日中立って現像していたら、その晩、足がつって大変だった」と言っていましたが、中高年になると、長時間立っていたり、歩きすぎたりするとその晩に足がつるという人が増えてきます。
足のつりは「有痛性筋けいれん」といって文字通り、痛みを伴った筋肉の過剰収縮で強い痛みを伴います。若いうちは激しい運動をした後に起こるのですが、中高年になると普段より少し頑張っただけでも起こるようになってきます。
ではなぜ中高年になるとつりやすくなるのか…。その原因を挙げてみましょう。
①筋肉量の減少
筋肉量は何もしないと20代をピークに徐々に下降していきます。しかし歳を取ったからといって筋肉がつかないということではありません。ちゃんと動かせば筋肉は維持はできます。だから毎日適度に身体を動かしましょう!中でも毎日歩くことが一番の足のつり予防法だと私は思います。しかし「たまにしか歩かないから、こういう時にまとめて歩いてしまえ!」と、こういう人が明け方に足がつります。
②水分・ミネラル不足
中高年の方が口を揃えて言うのが「明け方に足がつる」とうこと。人間は一晩でコップ一杯の汗をかくと言われています。つまり明け方には身体の水分量が低下してくる。するとつりやすくなるのですね。だから寝る前には水を適量飲むことはとても大切です。水分やミネラルは筋肉の電気情報伝達に重要な役割をしていますから、不足すると伝達が上手くいかず、筋肉が過剰収縮を起こしやすくなるのです。
また、私がお勧めするミネラルは「海藻」や「鰹節などのだし汁」。これらのミネラル分が日本人にとって一番吸収率が高いので積極的に摂りましょう!ちなみにミネラル分を摂らない偏食をしている人に足がつりやすい傾向があります。
③冷え
当院の患者さんを見ていても、上半身は手厚く着ているのに、下半身は薄着という人が多いですね。
外出時、首にマフラーをするように足首にもレッグウォーマーをしてあげましょう!膝下の冷えは足のつりにつながります。
④糖尿病・肝腎の病気
これらの病気を持っている人は足がつりやすいといわれています。また、腰のヘルニアや脊柱管狭窄症の人も足の血流がわるくなるため、足がつりやすくなります。
以上が主な原因となります。次に足がつってしまった時の対処法ですが「ふくらはぎ」や「足の裏」、「太もも裏」の場合、寝ていたら頑張って立ってください。そして立位でつった筋肉をゆっくりと伸ばします。あくまでもゆっくりと伸ばしてください。そして部屋の中をウロウロと歩いていると緩解してきます。「すね」や「足の甲」の場合は正座をすると治ります。
これらの筋肉の中で私の経験から一番大変だったのが「太もも裏」がつったとき。この筋肉がつるとそれはそれは激痛でした。もう二度とつりたくはないですね。この「太もも裏」の筋肉は階段を昇ることで鍛えられますので、つり予防として定期的に階段を昇り鍛えておくことをお勧めします。
しかし、①~④の原因に気をつけても頻繁に足がつってしまうという人は漢方薬の「芍薬甘草湯」を試してみてはいかがでしょうか?ドラッグストア等で販売しています。芍薬や甘草は筋肉の収縮を弛めてくれる効果がありますので、薬剤師、登録販売者に相談してみて下さい。
このように、足のつりというのは誰もが経験するような身近にある症状です。
足がつりやすくなるこの季節。適度に筋肉を動かし、水分ミネラルを摂り、下半身を冷やさないようにお過ごしください。